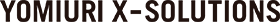PICKUP
WHAT’S NEW最新情報
STORYストーリー
-

元気なシニアが大手町に集合 「よみうりAGELESS DAY 2024」
ストーリー
2024.4.15
-

「最強」新聞2紙に掲載された「最強対最強」集英社「呪術廻戦」
ストーリー
2024.4.15
-

ネット時代の「選ばれる1社」へ センチュリー21が「こども絵画コンテスト」を主催
ストーリー
2024.3.19
-

新聞広告を顧客活性化の起爆剤にショップチャンネル「全員送料無料」キャンペーン
ストーリー
2024.3.19
-

【レオナール】国内最大級旗艦店のオープン告知に「マリ・クレール」を活用
ストーリー
2024.2.19
-

サテライトオフィスがオンラインイベントに特別協賛 ブランディングとリード獲得を目的に1万人集客
ストーリー
2024.2.19
MEDIAメディア